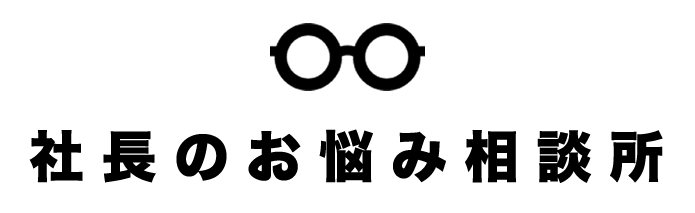確定申告における個人事業税の処理について
2017.10.9

個人事業主の場合、「個人事業税」という税金を支払わなくてはいけません。
これは、法律で定められた70の業種のみが課税されるものです。
この個人事業税とは、確定申告において経費として計上することができます。
また、個人事業税を支払った時には「租税公課」の勘定科目を使って処理することができます。
そこで、確定申告における個人事業税の処理について、その他個人事業税の納税額の計算方法や控除額などについてもご紹介致します。
スポンサーリンク
こんな記事もよく読まれています
-

-
確定申告を遡り申告する際の期限や源泉徴収票、必要書類について
確定申告は期限内に正しく申告することが最も大切ですが、様々な事情で確定申告間に合わない場合もあるでし...
スポンサーリンク
確定申告において個人事業税は必要経費になる
個人事業主は、所得税や住民税の他にも個人事業税という税金を納めなくてはなりません。
この個人事業税とは確定申告の際に、必要経費として認められます。
そこで、個人事業税が経費として認められる理由や控除額についてご紹介致します。
個人事業税とは確定申告で経費にできるのか?
個人事業主は、毎年8月と11月に「個人事業税」を納めなくてななりません。
「個人事業税」とは、「所得税」と「消費税」が国に納める国税であるのに対して、地方に納める地方税になります。
また、「個人事業税」とは、事業に関わる税金なので、「租税公課」として経費にできます。
個人事業税は確定申告で必要経費になる
確定申告で納める税金では、所得税や個人住民税などは経費として認められません。
しかし、個人事業税とは、事業に関して発生した経費として認められます。
ですから、確定申告において漏れはないように、必要経費として算入しましょう。
確定申告で個人事業税以外の税金は経費にならない
個人事業税以外住民税や所得税は経費として認められません。
これは、事業とは関係なく支払う義務があるからです。
また、個人事業税の他にも「印紙税」も必要経費になります。
さらに、自宅で事業を行っている場合、「自宅の固定資産税」は事業での使用分のみ必要経費として認められます。
個人事業税を課税される業種について
個人事業税とは、個人事業主のうち、法律で定められた70の業種のみが課税されます。
そして、その70の業種も3つに区分され、それぞれの区分ごとによって税率が決められています。
法定の業種に該当しているかどうかは、事業所がある都道府県において確認しましょう。
個人事業税の控除額について
個人事業税の控除額とは、一律290万円と定められています。
事業をはじめて1年未満の事業所の場合は、1ヶ月24万2千円の控除になります。
1年間の利益が290万円以下になる個人事業主については、個人事業税を支払う必要はないということです。
確定申告において個人事業税が租税公課になること
個人事業税とは、確定申告の際に租税公課として経費に計上することができます。
租税公課とは、経費として計上することができる税金や負担金のことをいいます。
そこで、確定申告において個人事業税が租税公課になることや個人事業税の計算方法についてご紹介致します。
確定申告において個人事業税は租税公課になる
個人事業税とは、確定申告において経費として計上することができます。
このように、事業を運営する上で必要なものは租税公課として経費に計上することができます。
経費となる租税公課とは、個人事業税以外にも、不動産取得税や自動車税、固定資産税や印紙税などがあります。
確定申告で租税公課として認められる個人事業税
確定申告で必要な損益計算書の経費欄には、「租税公課」の項目がトップにあがります。
租税公課とは、経費で落とすことができる税金や負担金のことであり、個人事業税はこれにあたります。
個人事業主税は業種により3~5%課税され、納付書は8月と11月の年2回送られます。
確定申告でわかりやすく個人事業税は租税公課で仕分ける
個人事業主の税金の仕訳は、必要経費として認められるかどうかにより勘定科目が異なります。
そして、必要経費として認められる税金については「租税公課」として仕訳されます。
このように、わかりやすく仕訳しておけば確定申告の際に、経費としての計上漏れがないでしょう。
個人事業税の計算方法とは
個人事業税の納税額の計算方法とは、前年の事業所得より事業主控除290万円を引いたものに税率を乗じます。
事業所得とは、事業の売上から必要経費を引いた額になります。
また、事業主控除とは、個人事業主であれば誰でも認められる控除であり、290万円の控除を受けることができます。
事業と個人の両方で使っているものは按分
事業と個人の両方で使っているものについては、事業として使っている分だけを按分して、それを租税公課として計上することができます。
例えば、自動車税や自動車取得税、固定資産税などは自宅用と仕事用とに按分して、事業用(仕事用)を租税公課、それ以外の個人用を事業主貸として処理しましょう。
確定申告における個人事業税の勘定科目について
確定申告をする際に、支払った費用などについて勘定科目を用いて仕訳をする必要があります。
個人事業税とは、「租税公課」勘定を使い経費として処理します。
経費として計上できない税金の勘定科目などについても合わせてご紹介致します。
確定申告による個人事業税の勘定科目とは
個人事業主が事業によって得た所得や不動産所得などに応じて課税される地方税のことを個人事業税といいます。
個人事業税の支払額はすべて経費として処理することができます。
ですから、個人事業税を支払ったときの勘定科目とは、「租税公課」勘定を使い記帳しましょう。
確定申告において個人事業税の延滞税の勘定科目とは
個人事業税の納付が遅れてしまうと、延滞税を支払わなくてはいけません。
この場合、その延滞税の金額は経費として計上することはできません。
延滞税を事業用の口座から支払った場合は、経費とならない支出なので「事業主貸」勘定を使い処理しましょう。
確定申告で個人事業税の勘定科目「租税公課」とは
租税公課とは、経費として落とせる税金や負担金のことであり、「租税」と「公課」を合わせた勘定科目です。
「租税」とは、国や地方が法律に則り所得や財産などから徴収する税金です。
「公課」とは、国や地方公共団体に対する交付金や会費などのことです。
経費に計上できない税金の勘定科目について
経費に計上できない税金を支払った場合は、「事業主貸」という勘定科目で処理します。
社会保険料については、事業主の国民年金や国民健康保険は「事業主貸」として処理するのですが、個人事業主の所得税の確定申告上では社会保険料控除の対象になります。
勘定科目がわからないときは
費用について、どの勘定科目を使うべきか判断に困った時は、自分の判断により勘定科目を決めても問題ありません。
基本的には、すでに使用している勘定科目を使用して仕訳をしますが、足りない勘定科目がある場合は必要に応じて追加しても良いでしょう。
大事なのは「その支払いが事業にとって必要なものであるかどうか」ということです。
- カネの悩み