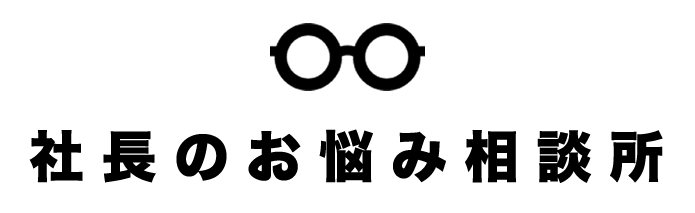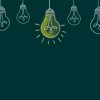確定申告をきちんとしないと追加納税が必要になる場合も
2017.9.12

確定申告の提出が遅れたり、修正があったときにはどんなペナルティがあるのでしょうか?
追加納税となる原因や種類とは?追加納税の計算方法やいつまでに確定申告や納付をしたらいいかを紹介します。
スポンサーリンク
こんな記事もよく読まれています
-

-
確定申告へ行こう!家賃収入で〇〇円以上の場合は申告しないと悲劇が起こります!
不動産投資として人気のアパートやマンション経営。サラリーマンの人でも家賃収入を得ることができる、と話...
スポンサーリンク
確定申告をして追加納税となる原因にはどんなものがあるのでしょう?
確定申告をしたからといって安心してはいけません!?
税務署から指摘されると追加納税は決定的?
追加納税となる原因にはどんなものがあるのでしょうか?
確定申告で追加納税となる原因はさまざま
期限内に申告書を提出していても、その内容に誤りがあり税務調査で指摘されたときには修正申告をしなければいけません。
過少申告加算税は、修正申告や更生によって追加で納付しなければいけない税額があるときの附帯税となります。
附帯税とは、申告期限までに申告書を提出しない、納期限までに税金を納付しないなど本来納めるべき税金の他に課されるもので、簡単に言えばペナルティーです。
確定申告の追加納税の原因は納付期限を守らないこと
税金を納付期限までに納められなかったときには延滞税がかかります。この納付期限には2段階あり、納付期限より2ヶ月以内に納めた場合と、納付期限より2ヶ月以上経過してから納めた場合では延滞税率が変わるので注意が必要です。
確定申告で追加納税の原因となる納付遅れ
源泉所得税の納付が遅れた場合は不納付加算税という罰則的税金が追加でかかります。
不納付加算税が5,000円未満の場合や過去1年間に納付遅れがなかった、納付期限から1ヶ月以内に納付した場合や新たに源泉徴収義務者となり初回の納付であり納付期限から1ヶ月以内に納付した場合は不納付加算税が免除されることもあります。
確定申告の追加納税の原因となる最もしてはいけないこと
嘘の申告書や事実を隠ぺいしたものを提出したときには「重加算税」がかかります。この重加算税は故意にしたかどうかが判断基準なので、間違いやミスの場合は重加算税とされれることはありません。
売り上げをわざと抜いたり、架空の仕入れや経費を作ってはいけません。領収書を偽造するようなことも故意に脱税した事になってしまいます。
追加納税の原因は確定申告をしないこと
確定申告書は申告期間内に提出することが原則です。この期間内に確定申告書をしなければ納めるべき税額プラス無申告加算税がかかります。
正当な理由があるときや2週間以内であれば、無申告加算税がかからないこともあります。無申告加算税がかかる場合は同時に延滞税も支払わなければいけません。
確定申告で追加納税がかかるときの計算方法について
確定申告後に追加納税がかかるときの計算方法とは?
追加納税の種類によって計算方法は変わってきます。
知らないだけで、税率も変わってきます。追加納税をできるだけ抑えるにはどうしたらいいのでしょうか?
確定申告で追加納税がかかないように所得税の計算方法を覚えておきましょう!
個人事業主にとって最も大きな税金となる所得税ですが、所得税額は自分で計算し納付しなければいけません。
所得税の計算式は
・収入 − 必要経費 − 各種控除 = 課税所得金額
・課税所得金額 × 税率 − 課税控除額 = 所得税額
となります。
1年間の収入から必要経費と所得控除などを差し引いた金額が、課税所得金額となり課税所得金額に応じて税率が決まります。
確定申告後に追加納税がかかる場合、過少申告加算税の計算方法は?
過少申告加算税の計算
追加で支払う金額が50万円までであれば10%課税され、50万円を超える部分には15%の割合で課税されます。
税務署で事前に相談していてその証拠があるなどのような正当な理由がある場合や自主的に修正申告した場合は課税されないケースもあります。
不納付加算税の計算
不納付加算税は納付しなければならない源泉所得税の10%となります。税務調査などで税務署から言われて納付するのではなく、納付が遅れてしまったことに気づき自ら納付した場合は、不納付加算税が本来の10%から5%に下がります。
確定申告をしていなくて追加納税がかかる場合の計算方法は?
無申告加算税を支払うときには、納付すべき税額が50万円までであれば15%を納める必要があり50万円を超える部分については20%の割合で課税された金額を納めなくてはいけません。
税務署から調査を受ける前に自主的に期限後申告をすれば、納付すべき税額の5%と加算税率の割合が軽減される場合もあります。
確定申告でこれだけは避けたい重加算税!
重加算税の計算は、ごまかした税額の35%を上乗せとなります。これは期限内に申告していれば過少申告加算税に代えて35%という意味です。
100万円の本税がある場合は100万円プラス35万円支払わなければいけません。
申告をせずに税務調査が入った時に納付すればいいと考えていると大きなダメージを受けてしまいます。
追加納税がある場合はとにかくできるだけ早く納付することが重要!
延滞税の割合は、納付期限より2ヶ月以内に納付した場合であれば2.8%、納付期限より2ヶ月以上経過して納付した場合はなんと9.1%まで跳ね上がります。
平成26年から延滞税の割合や利子税の割合が改正され、負担が軽減されてはいますが税金を納付期限までに納めることが大切です。
確定申告の納税はいつまで?追加納税とならないために
確定申告と納税はいつまでに済ませておけばいいのでしょうか?
追加納税にならないためには、きちんと期限を把握しておきましょう。
確定申告と納税を同時にすることで期日が過ぎることなく申請や納付ができるようです。
追加納税にならないために確定申告の納税はいつまでにするべき?
平成28年分確定申告分の納税の期限は、所得税及び復興特別所得税が平成29年3月15日(水)、消費税及び地方消費税が平成29年3月31日(金)、贈与税が平成29年3月15日(水)でした。
申告の期間は毎年だいたい2月16日~3月15日頃です。
納税の期限は確定申告書の提出期限と同じ日となり、申告書を提出した後に税務署から納付書の送付や納税通知書等によるお知らせが来ることはありません。
確定申告で追加納税にならないためにはいつでも払えるコンビニよりも自動で引き落としがおすすめ
納めるべき税金を納期限までに納めなければ延滞税が課せられてしまいます。税金を納める方法は現金で払う方法と銀行口座から振替納税する方法、インターネットバンキングでの支払い方法があります。
現金で支払う場合は、確定申告書に同封されている納付書を添えて税務署の納税窓口や郵便局や銀行で納税手続きを行いましょう。
30万円以下であれば、コンビニで支払うことができます。
確定申告がいつまでかがわかっているなら追加納税は怖くありません
国税を納付する期日を気にしなくていいのが、自分の銀行口座から自動で引き落とす振替納税となります。
預金口座振替依頼書を税務署及び希望する預貯金口座の金融機関へ提出しましょう。わざわざ税務署や銀行に行かなくてもすみますね。自動的に次回以降も振替納税ができます。
住所変更などで所管の税務署が変わる場合は再提出しなくてはいけません。
確定申告のときに税金を支払えないときは?
確定申告のときに税金を全額支払えないときの対処方法として延納制度があります。確定申告書の延納の届出欄に記入することで税金の支払いを一部待ってもらえます。
この延納制度には限度額があり、遅れたぶんは利子がかかります。
確定申告の期限は毎年3月15日ですが、この日までに、納税額の2分の1以上を納付していなければ延納制度は使えません。残りの金額の期日はは5月末までとなっています。
期限通りに納付できなかった部分については、法定の利子税が加算されます。実際にどれぐらいになるのかは、延納の相談をするときに確認しましょう。
延納制度を利用する場合もできるだけ、多く納税はしておいたほうがいいことがわかりますね。
ついつい忘れてしまう確定申告の納税期間の注意点は?
納税が遅れた場合は、所定の税金を納めるまでの日数分だけ延滞税がかかります。口座からの振替納税は期日を守るための有効な対策となりますが、残高不足であれば未納扱いになってしまいます。
納税の期日は年度によって日にちがずれることもあるでしょう。期日で憶えておくのではなく、確定申告書の提出期限と納税の期限は同じとしておくことで納付忘れを防げるでしょう。
- カネの悩み