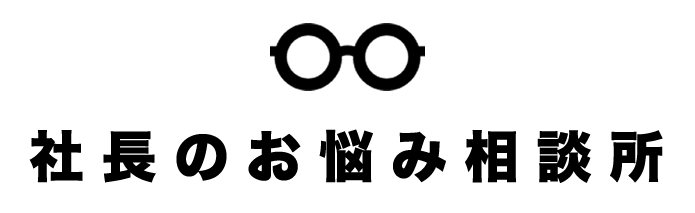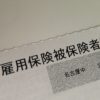雇用保険と労災の違いとは?雇用保険の料率の計算方法
2017.10.3

雇用保険や労災保険とはどんなものなのでしょうか?
このふたつがセットになっている理由とは?なぜ労災保険料は事業所が全額負担となるのでしょうか?
雇用保険や労災保険の違いや労働保険の意味、料率や計算方法について紹介します。
スポンサーリンク
こんな記事もよく読まれています
スポンサーリンク
雇用保険と労災保険の違いは負担額?労働保険について
雇用保険や労災保険は、労働者と事業所を守る心強い保険です。
雇用保険と労災保険の意味や違いにはどんなものがあるのでしょうか?
雇用保険や労災保険の対象者となるのは?
労災との違いとは?雇用保険について
雇用保険とは、労働者を失業させないように働きやすい職場を保ったり能力を向上させる目的があります。
また、失業や職業教育訓練を受けるときでも安定した生活が送れるようにするための保険制度となります。
雇用保険は、失業したときには雇用されていた事実の証明となり、働く意欲があっても働く場所がない現状に対して支払われる給付金を受けるための納付「失業保険」とも呼ばれています。
雇用保険との違いとは?労災について
では、労災保険とはどんなものなのでしょうか?
労災保険は、労働者が業務中や通勤中に何らかの損害を受けたとき厚生労働省からの認定を受ければ、保険料が支給されるものとなります。
万が一のときに備える医療保険のようなものとなり、事業主が毎年保険料を支払います。
労災は労働者の保険となりますが、事業主を守るための保険でもあります。労働者が業務上にケガなどをした場合は、事業主は補償を行う義務があり全て負担となるものを労災保険となる国が補償してくれます。
雇用保険と労災の違いは加入の条件
雇用保険は、労働者がある一定の条件を満たしている場合に加入の義務があります。労働者が加入を希望していなかったり、パートやアルバイトだからといって雇用保険に入らないということはできません。
雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間以上である事と31日以上引き続き雇用される見込みがある場合、加入の義務があるのに対し労災は家族以外の従業員が一人でもいる場合は必ず加入となります。未加入中で労災事故が起きた場合は、厳しいペナルティーが発生します。
雇用保険や労災保険の対象者について
雇用保険の対象となるのは、1週間の所定労働時間が20時間以上である事と31日以上引き続き雇用される見込みがある場合ですがこのような場合は対象外となります。
・季節的に雇用され、4か月以内の期間と決めて働く場合もしくは1週間の所定労働時間が30時間未満
・昼間、学生である事
・65歳以上で新たに雇用する場合
労災保険の対象者は、正社員、パート、アルバイト派遣など名称や雇用形態に関係なく労働の対償として賃金を受ける者すべてとなりますが代表権・業務執行権を有する役員については適用されません。
雇用保険と労災どちらにおいても、事業主と同居している親族は原則として労働者とはなりません。
雇用保険料や労災保険料を支払っていない場合は?
雇用保険料は、事業所だけでなく従業員の負担もあり従業員の賃金から保険料を控除し
事業所が国へ支払うものとなりますが、労災保険料は全額すべて事業所の負担となります。
事業を始めて、雇用保険料や労災保険料を支払っていない場合は過去2年分の保険料を請求される可能性があります。
保険料の徴収に関して時効は2年間となるため、過去2年分の保険料をさかのぼって支払らう義務があるという事になります。
雇用保険と労災保険はセット?違うものなのになぜセットで納付?
雇用保険と労災保険は、違うものなのになぜ申告や納付が一緒になるのでしょうか?
申告の窓口や行く順番について紹介します。
申告忘れは、ペナルティがとんでもない事になってしまう可能性が!?
雇用保険と労災保険がセットなのは労働保険となるため
雇用保険と労災は別のものなのに、どうしてセットとしての認識が高いのかというとこのふたつをまとめたものが労働保険となるからです。
雇用保険と労災はセット加入となります。ただし、建設業などの一部業種を除きます。
セットで加入するのですが、手続きは別のものとなります。
労働保険は、従業員を雇い始めたら加入手続きをはやめにするようにしましょう。必要書類は、登記事項証明書、事業主の住民票、タイムカード、事務所の賃貸契約書コピー、税金関係の届け書一式、その他、役所が要求する書類となります。
セット加入となる雇用保険と労災の加入の流れ
労災保険と雇用保険の対象となる場合、どちらか片方だけ加入する事はできません。必ずセットで加入となりますが、雇用保険の窓口は公共職業安定所となり労災保険の窓口は労働基準監督署となります。
雇用保険と労災保険となる労働保険を仕切るのは、労働基準監督署となるので加入の相談をするときは労働基準監督署に聞きましょう。
雇用保険・労災保険の加入の流れは、その年度中のおおよその人件費を集計表の形にまとめておきます。労働基準監督署で労働保険・労災保険の手続きをし、控えと、保険料の振込用紙をもらいます。
それから、公共職業安定所へ行き雇用保険の手続きをして保険料を払います。
労働基準監督署→公共職業安定所(ハローワーク)の順番となります。
雇用保険と労働保険はセットで手続き!提出期限とは?
労災保険は労働基準監督署に書類提出となります。
労働保険関係成立届(住民票添付)、適用事業報告は従業員雇用の日から10日以内となり、労働保険概算保険料申告書は従業員雇用の日から50日以内になります。
雇用保険はハローワークに書類提出となります。
雇用保険適用事業所設置届(労働保険関係成立届などの添付)、雇用保険被保険者資格取得届(労働者名簿、雇用契約書などを添付)は従業員雇用の日から10日以内となります。
雇用保険と労災はセットで申告・納付
雇用保険料・労災保険料は、労働保険料としてセットで年に1度、毎年6月1日~7月10日の間に前年度分をまとめて申告・納付しなくてはいけません。
二元適用事業の場合は、労災保険料と雇用保険料を別々に納付となります。
概算保険料の額が40万円以上もしくは、労働保険事務を労働保険事務組合に委託している場合は、3回に分割して納付することが可能です。
労災保険料は全額事業主が負担となるので、労働者に一部でも負担させた場合は違法行為にあたります。
事業主が労災保険の加入をしていなかった場合
事業主が労災保険への加入手続きをしていなくて、その期間中に業務災害又は通勤災害
が起きてしまった場合、支給された保険給付額の40%相当額が、その事業主から徴収されることになります。
事業主の故意もしくは重大な過失により起きた業務災害である場合は、支給した保険給付額の全部、又は一部を事業主から徴収となります。
雇用保険と労災保険の料率が変わるのなぜ?
雇用保険と労災保険の料率はどのように決められるのでしょうか?
雇用保険と労災保険の料率や負担する割合とは?
料率が異なる理由や計算方法、納付の仕方や加入の確認方法について紹介します。
雇用保険と労災保険の料率や負担する割合について
労働保険の給付は労働基準監督署、公共職業安定所となりますが保険料の申告・納付は、 労働保険料として一括となります。
雇用保険の保険料率は業種により異なります。
一般の事業は、保険料率が9/1000、事業主負担は6/1000、労働者負担は3/1000となります。
農林水産・清酒製造の事業は、保険料率が11/1000となり事業主負担が7/1000、労働者負担が4/1000となります。
建設の事業については、保険料率が12/1000、事業主負担が8/1000、労働者負担が4/1000になります。
労災保険は全額、事業主負担となり保険給付の額については賃金総額により保険料を計算し、労働者がもらっている賃金により決まります。
雇用保険料や労災保険料は料率から計算を
雇用保険の被保険者である従業員の賃金×雇用保険料率=雇用保険料
労災保険の被保険者である従業員の賃金× 労災保険料率=労災保険料
雇用保険料率は、雇用保険受給者の人数や積立金の状況によって厚生労働大臣が決めるため、毎年4月1日に改定が行われますが変更のある年とない年があります。
労災保険料率は、事業の種別により労災の危険性が変わるので業種によって料率が細かく分かれています。
雇用保険料と労災保険料の合わせたものが労働保険料となります。
雇用保険や労災保険の料率が異なる理由
雇用保険は、一般の事業・農林水産や清酒製造の事業・建設の事業の3つに分かれていて農林水産・清酒製造・建設のどれにも当てはまらない事業が一般の事業となります。
一般の事業の保険料率に比べ、農林水産・清酒製造の事業と建設の事業の保険料率が高いのはこんな理由からとなります。
農林水産・清酒製造のような事業は季節によって事業規模が縮小したり就業状態が不安定となりやすいため、失業給付を受ける可能性が高いことから保険料率が高くなっています。
季節的な休業や事業規模の縮小がない牛馬育成、酪農、養鶏、または養豚の事業や園芸サービスの事業、内水面養殖の事業、船員が雇用される事業は農林水産の事業のなかでも、一般の事業として取り扱われます。
建設業の場合は、建築物ごとの雇用契約のケースが多いため失業給付を受ける可能性が高くなるので保険料率も高くなります。
雇用保険や労災保険の納付は口座振替も可能
雇用保険や労災保険である労働保険は、金融機関や労働局の窓口以外に口座振替での納付もできます。
口座振替で納付する場合は、口座番号を記載した申込用紙を口座の開設した金融機関の窓口に出してください。
労働保険の法定納期限を過ぎても督促状の指定期限までに完納すれば延滞金はかかりませんが、納付忘れを防ぐためにも口座振替がおすすめです。
雇用保険や労災保険は事業者と労働者のためのもの
労働保険は事業者が申告や納付をしているため、労働者は雇用保険や労災保険を使うときにだけ気にするものなのかもしれません。
しかし、労働保険に加入しているかどうかは厚生労働省のホームページの労働保険適用事業場検索から確認することができます。
事業場の都道府県、事業主名、法人番号、所在地等の検索条件を入力すれば労災保険、雇用保険の適用状況が表示されるので従業員にこのような確認方法があることを教えてあげましょう。
都道府県の労働局や労働基準監督署でも確認することができます。
- ヒトの悩み