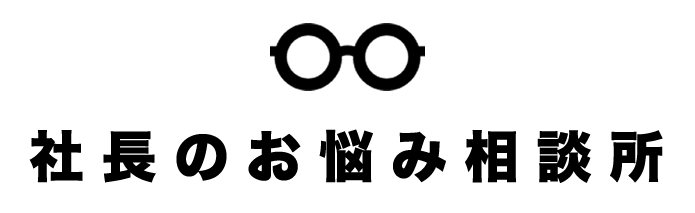確定申告で迷わない自動車税などの経費項目について
2017.9.27

事業用とプライベートと両方に使用している自動車の場合は、経費としてどのように計算したらいいのでしょうか?
自動車税の勘定科目や項目を確定申告のときにわかりやすく経費として計上するには?
自動車にかかる費用を経費とするときのポイントを紹介します。
スポンサーリンク
こんな記事もよく読まれています
-

-
確定申告で通帳のコピーは必要?青色申告するなら持参しましょう
確定申告をするときには銀行の通帳は持っていくべきなのでしょうか? 青色申告するなら、通帳とコピ...
-

-
青色申告取りやめ届出書とは?法人成りで事業再開する際は注意!
確定申告には、青色申告と白色申告の2つがあります。それぞれにメリット・デメリットがありますが、法人成...
スポンサーリンク
確定申告で自動車税を経費として計上するには?
確定申告で自動車税は経費の対象になるのでしょうか?
自動車を事業用としても個人用としても使っている場合の計算方法を紹介します。
自動車税を経費とするときのポイントにはどんなものがあるのでしょうか?
自動車税は経費?確定申告ではどのように計算?
自動車税は、自動車を保有している人が納める税金となり金額は排気量や自家用・営業用かによって違ってきます。
事業で自動車を使う場合は、自動車税を必要経費とでき個人用としても使う場合は事業用の使用割合分だけ必要経費とできます。
使用割合は週または月のうち何日仕事に使用するかとなります。
個人用として使う部分と仕事で使う部分をハッキリと分ける事が難しい経費は、家事関連費と呼ばれていて個人用としても事業用として自動車を使っている場合は経費もその中のひとつになります。
車の経費に含まれるのは、ガソリン代、駐車場代、修理費、自動車税、自動車保険料、使用率で按分した車の購入費の減価償却費です。
業務使用中の高速料金や駐車料金も経費となります。
計算方法は、ガソリン代等=ガソリン代等×使用割合
減価償却費=車の減価償却費×使用割合
確定申告で自動車税を経費として計上する方法
自動車は、事業のみに使用しているのであれば経費を按分する必要はありませんが個人でも使用している場合は自動車税はもちろんのこと、軽自動車税、自動車取得税、重量税や車にかかる維持費なども按分する必要があります。
決算のときには、計上し忘れていないかどうかしっかり確認しましょう。
確定申告で自動車税を経費とする場合のポイント
個人事業主や法人で車を購入するときには、なぜ車が必要なのかをハッキリさせておく必要があります。
この理由がきちんとしていないと、節税対策と疑われてしまう可能性があるからです。
事業で車を使う目的にはいろいろありますが、営業まわりのため車や役員の出退社の送迎用車、車がないと事業そのものが成り立たない場合などが理由としてあげられます。
車を購入する前には、どのように事業と関連しているのかや必要性をきちんと説明できるようにすることが大切です。
自動車の経費を計上をするときに気をつける事とは?
事業用に自動車を購入した場合、税金・保険・各種手続き費用等の経費がかかります。また、管理を維持するためにガソリン代や駐車場代などの経費もかかります。
自動車の車両本体は固定資産となるため、減価償却の対象となり毎年償却額に相当する分を経費として計上しなくてはいけません。
減価償却の年数や償却費を計算するには、車両の用途や種別によって決められた法定耐用年数を確認しましょう。
普通自動車であれば6年、軽自動車は4年、二輪車または三輪車は3年、自転車は2年となります。
事業用に車を購入して、節税対策をしているつもりが考えているより経費とならずに税金の負担が大きくなってしまうケースもあるのでタイミングや年数によって価値の下がる資産という事を忘れないようにしましょう。
自動車の保険代は経費にできるのでしょうか?
自動車保険は、一つの車両に2つの損害保険をかけることはできないため、社用車にかけた自動車保険を経費として計上できます。
営業用車両ナンバーで緑に白文字や黒字に黄色文字などの車両の事業用任意自動車保険は経費となりますが、一台の車を個人用・事業用として使っているような場合は自動車保険料も按分する必要があります。
このときには自動車税の使用割合と同じ割合で計算しましょう。
経費としての自動車保険料は事業所得から差引けるので確定申告のときには申告し忘れないよう気をつけてください。
確定申告で自動車税の勘定科目はどう仕訳るべき?
自動車税の勘定科目はどのように仕分けたらいいのでしょうか?
確定申告で、自動車にかかる費用を経費としてわかりやすくするには?
勘定科目を勘違いしないためのポイントを紹介いたします。
確定申告の自動車税の勘定科目とは?
事業車の自動車税を支払った場合は、租税公課勘定を使って記帳し自動車や車両に関連する費用をまとめて車両費としているのであれば自動車税も車両費となります。
業務で使用している車両の自動車税5万円を現金で支払ったときの仕訳の方法は、借方に租税公課、金額5万円とし貸方に現金、金額5万円となります。
車両費として記帳している場合は、借方に車両費、金額5万円として貸方に現金、金額5万円とします。
個人事業主で、事業用・個人用と車を併用している場合は、節分します。
自動車税を現金で5万円支払った場合は、事業用の使用率が7割として計算すると借方に租税公課3万5千円、事業主貸1万5千円とし貸方は現金5万円となります。
このときに摘要で自動車納付税と書いておきましょう。
確定申告でわからなくならないようにするには?自動車税の勘定科目
自動車にかかる税金を支払ったときには租税公課という科目で帳簿に記載しますが、購入費用や車検の支払いと一括して支払う場合は税金以外の支払い含まれてしまうので注意が必要です。明細は分かれて書かれている事が多いので確認しましょう。
自動車税、自動車取得税、自動車重量税、印紙や証紙などの記載される検査手数料は租税公課ですが、車検のときの部品交換代や修理費の勘定科目は修繕費や車両費となります。
どちらも経費として計上できますが、記帳するときには科目が違う事を覚えておきましょう。
確定申告で自動車税などの勘定科目で迷ったときは・・
自動車税のような税金は租税公課として、勘定科目がハッキリしていますが車の修理代のようなものは修繕費と車両費のどちらにすればいいか迷ってしまう事もあるかと思います。
そのつど、どちらなのか迷うことのないように決めてしまうといいでしょう。勘定科目のとりきめは特に決まりがありません。会社の裁量に任されているので、一度決めたら違うものに変えない事が大切です。
車両費の勘定科目を設けているのであれば、車の修理代やタイヤ代は車両費となります。
自動車の勘定科目の上手な決め方とは?
勘定科目の判断が難しいときには、自分の判断で勘定科目を決める事ができます。このときに大切なのは、勘定科目のズレではなく事業に必要な支払いかどうかがポイントとなります。
一般的に使われている勘定科目であっても、別の勘定科目で管理した方がやりやすいのであれば変えても大丈夫です。
また、勘定科目が足りないときには増やす事もできます。
確定申告のときに提出する青色申告決算書には勘定科目を追加できるようになっています。
自動車関連税・ガソリン代・保険料等、車に関する費用を車両費と記帳するには勘定科目を追加しなければいけません。
一度決めた勘定科目や仕分けのルールはきちんと守りましょう。
自動車を購入するときの勘定科目の違いとは?
仕事で使う自動車を購入する場合、新車か中古車で仕訳は変わるのでしょうか?どちらの車を購入しても仕訳に違いはありませんが、減価償却の計算に用いる「耐用年数や償却率」や、自動車取得税の金額が異なります。
車両本体価格や付属品価格などは、購入対価となるので車の取得価額に含まれます。それ以外の費用で車両の取得価額に含まれないものに注意しましょう。
自動車取得税と登録のために要する費用は購入時の経費にもできますし、取得価額に含めて減価償却として経費化できます。
購入時の経費とした方が、購入した年度の税金を安くできますが最終的に経費となる金額は変わらないのでどちらがいいのか考慮する事が重要です。
確定申告で自動車税の項目はどこにあてはまる?
確定申告をするときに自動車税や保険料などはどの項目になるのでしょうか?
経費項目にあてはまらないものとは?
事業用の自動車を購入するときに気をつける事や自動車保険について紹介します。
確定申告で自動車税は租税公課ですが経費項目とならないものとは?
自動車税をはじめとして、一般的に車にかかる費用は経費として計上できますが公的な罰金、科料、過料などは経費にはできないので注意しましょう。
スピート違反や駐車違反などの交通反則金は経費となりません。
しかし、事業の相手との契約不履行であったり契約違反としての罰金は民事上の契約に基づく支払いとなるので必要経費にすることができます。
公的なペナルティの罰金は経費にできません。
駐車違反の反則金は経費にできませんが、レッカー移動に費用がかかったときには経費にすることができます。
確定申告で経費の項目となる自動車税や仕訳について
車両費は、自動車にかかる経費をまとめた勘定科目となりますがわかりやすいように仕訳をしてもかまいません。
車両費に該当するのは、自動車に関連する税金・保険料・修理費用・車検代・ガソリン代・その他車両維持費などになります。
自動車に係る費用を車両費としてまとめない場合は、自動車保険は損害保険料、自動車税は租税公課、修理費用は修繕費、ガソリン代は消耗品費という仕訳になります。
勘定科目別に細かく振り分け項目を増やすことで車両費だけ目立つ事が防げます。
確定申告では自動車税の項目、日割見合の金額に注意
自動車税は、租税公課という勘定科目で処理をしますが購入したときの自動車税の見合金額は租税公課にできないので注意しましょう。
自動車税の日割見合の金額を含めたものが自動車の取得価額となります。
自動車取得税は自動車の取得にかかる税金なので取得時の損金として処理できるのに対し、自動車税見合いの金額は税とならず支払金額の一部にあてはまる為租税公課にはなりません。
自動車税見合いを租税公課で落とすのは、損金過大となるので気をつけてください。
確定申告で経費に計上することができる自動車保険とは?
任意の自動車保険は、契約期間が1年以内であり支払日から1年以内に役務の提供を受けられれば支払日に必要経費となる損害保険料として損金算入できます。
毎年同じように損金算入する必要があり、都合の良いように仕訳を変えてはいけません。
自賠責保険は、保険期間が2~3年でも支払った年度に全額必要経費にする事が出来ます。
確定申告で経費としてわかりやすくしてくれるのが租税公課
租税公課は、国税や地方税・罰金などの公的な負担金のことを言いますが会計では必要経費として認められる税金になります。
租税公課として仕分けたものは、必要経費として計上できるので次回の確定申告では控除の対象となります。
固定資産税、不動産取得税、自動車税、登録免許税、個人事業税などがあてはまります。
- カネの悩み