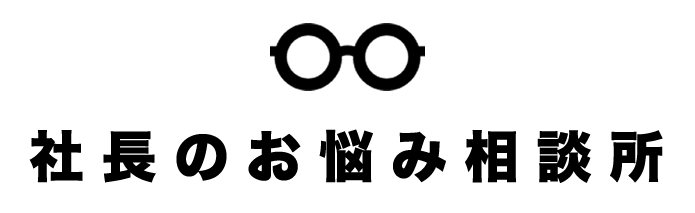ボーナス調査!2年目のボーナス、夏・冬の平均額とは
2017.10.5

社員が楽しみにしているボーナス。
夏と冬の2回支給が一般的ですが、入社1年目ではなく2年目から支給する企業も多く、その相場は中小企業ほど業績に左右されやすいものとなっています。
2年目のボーナス査定、夏・冬のボーナス平均額などについて調べてみました。
スポンサーリンク
こんな記事もよく読まれています
-

-
確定申告で通帳のコピーは必要?青色申告するなら持参しましょう
確定申告をするときには銀行の通帳は持っていくべきなのでしょうか? 青色申告するなら、通帳とコピ...
スポンサーリンク
ボーナス支給、入社2年目の平均額と企業のボーナス事情
ボーナスは企業の業績によって左右されやすく、ボーナス時期が同じであっても金額に大きな差が出てしまうのは仕方がないようです。
とはいっても気になるボーナスの額。入社1年目よりも2年目に期待が高まるのも無理はありません。2年目のボーナスの平均額などについて調べてみました。
ボーナスの疑問、入社2年目の平均額とは
入社1年目の平均給与が20万円前後、2年目にはそれに+1万円上乗せされた金額が相場になるため、平均給与額は21万円前後になります。
ボーナスの支給額は会社や職種によって差がありますが、例えば給料の4ヶ月分がボーナスと考えると、21万円×4ヶ月分=84万円となります。ただこれは大手企業や公務員の場合がほとんどで、入社2年目であってもボーナスがほとんどない会社もあります。
ボーナス支給2年目大卒の相場とは
入社2年目でボーナスが満額支給される大卒の場合、月収25万円、ボーナスは年間で×4ヶ月分の109万円支給されているようです。残業が増えることも影響し、入社1年目よりも年収は大きく上ります。生活も楽になるため、ローンを組んで車を購入する同期も現れる時期になります。
ボーナスは2年目から支給としている企業もある
入社1年目からボーナスを期待する社員も中にはいますが、1年目の社員には出さずに2年目以降にボーナスを支給する企業も多く、入社1年目はボーナスの代わりに「金一封」という形を取っているところもあります。
ボーナス支給は法律で決められたものではありませんが、社員の励みになる活力源の一つであることを覚えておきましょう。
ボーナス夏・冬支給は2年目以降からが一般的
新入社員はまだ会社に貢献していないという理由から、公務員を除く一般企業の場合、冬のボーナスから支給されるケースが多く、春夏のボーナス支給は2年目からが一般的です。
ただ企業の場合は、業績次第でボーナスが左右されるため、ボーナスを受け取れるかどうかがわからないのが現状です。
ボーナスが支給される2年目の6月は住民税に注意
注意したいのが住民税です。
前年に所得がない社会人1年目は住民税がかかりませんが、社会人2年目には前年の4月から12月の所得に対して住民税がかかります。
天引きは6月からはじまり、翌年の5月までの12ヶ月で年間の住民税を支払うことになります。
ボーナスに期待がかかる2年目の夏でも支給しない企業も多い
夏のボーナスを期待してしまう社員。一般的に夏のボーナスは2年目から支給されるところがほとんどですが、中小企業の場合、必ずしも支給できるとは限らないのが現状です。夏のボーナスの平均額、中小企業のボーナス事情について調べました。
新入社員の夏のボーナス、満額は2年目からが一般的
そもそもボーナスというものは、社員に対しる評価に基づいて支給額が決められるものです。入社間もない新入社員の査定をするには期間が浅いため、在籍期間を日割りで計算して5万円や10万円というように一定額を支給する企業が多いようです。夏のボーナスは入社2年目からが一般的です。
ただボーナスが2年目の夏にも支給される企業は少ないのが現実
ボーナスを基本給の1ヶ月分と設定している中小企業がほとんどのようですが、ボーナスの支給がそもそもないという中小企業も多いのが現状です。
日本の多くは中小企業が占めていますので、不景気の中であってもボーナスが少しでも支給できるのは恵まれている方なのかもしれません。
ただベンチャー企業などの場合、実力に応じて賞与を出すこともあります。
入社1年目の夏ボーナスを支給せず2年目支給にする理由
会社の規定がポイントとなります。特に大企業では賞与に関する在籍日数や支給日の詳細が明確に規定されていて、在籍要件が1月1日~6月30日、支給日要件が7月15日と明記されている場合があります。
4月1日に入社した新入社員の場合は、在籍要件が半分しか満たされていないため、ボーナスも半額支給となり、入社2年目以降は在籍要件が満たされるため満額支給という計算になります。
ボーナスは2年目の夏に必ず支給しなくてもいいとされている
賞与やボーナスを必ずもらえると勘違いしている社員も多いですが、給与とは違いますので、雇用契約書や労働条件通知書にボーナスに関する詳細を記載しておくことでトラブルを防ぐことができます。
採用時に確認を行うといいでしょう。ボーナス支給を「有」にしていても、業績によるものとすると記述してあれば問題ありません。
2年目に支給される新入社員の夏のボーナス、その平均とは
新入社員が気になる夏のボーナス。
ある調査によると、新入社員に最も近い20歳代前半のボーナス平均額は37万円、20歳代後半で60万円ということがわかりました。
ボーナス支給額多い業種トップ3は、公務員・金融業・製造業という結果に。
ボーナス査定は2年目の冬から同期との差をつける企業が多い
仕事にも慣れ始める入社2年目。2年目の冬のボーナスあたりから、同期との差をつける企業が多いようです。また、大企業に比べ冬のボーナスにシビアな中小企業ですが、中小企業ならではのメリットもあります。夏ボーナスとはちょっと違う、冬ボーナスについて調査しました。
2年目の冬のボーナスまでは同期との差はつけない
入社1年目は仕事や職場環境に慣れるのに精いっぱい。しかし2年目、3年目と過ぎると仕事もある程度慣れるので、同期の中で業績が下降してくる社員も出てきます。
ボーナスは実績や能力に応じて支給されるものなので、2年目の冬のボーナス当たりから徐々に差をつける企業がほとんどです。特に3年目になると部下を持ったり役職に就くなど同期との差も大きくなるので、ボーナス額も同期との差が付き始める時期になります。
中小企業が実現しやすい冬のボーナス2年目アップ
中小企業は大企業に比べボーナス面で金額に差が出てしまうものですが、中小企業ならではのメリットがあります。
社員は経営を間近で見ることができるため自分の勉強にもなりますし、大企業よりも実力をアピールしやすいため、自分自信の給料を上げる努力もしやすい環境と言えるでしょう。
社内業務も少ないのであれば、本来の仕事に没頭できますし、結果的に生産性もアップするのではないでしょうか。
1年目のボーナスより多い2年目冬のボーナス、その使い道とは
冬のボーナスを社員は何に使っているのか。その使い道は様々で、自分のご褒美として旅行や欲しいものを買ったりする人もいれば、将来に備えて貯金をする堅実な人もいます。
ただ以前ならボーナスを好きな事に全額つぎ込んでしまう人も多かったと思いますが、不況のため賞与の額も少なく給与自体伸びない会社も多いため、多少多い2年目の冬のボーナスを貰ったとしても、奨学金の返済やクレジットカードの返済に回すしかない社員も大勢いるのです。
ボーナスが2年目の夏より冬の方が多く支給される理由
会社が社員に対しボーナスを支払う理由、それは社員のモチベーションアップと節税です。儲けた分だけ税金を支払わなくてはなりませんが、ボーナスを支給することで必要経費として帳簿に載せることができ、また社員もボーナスを受け取ることで仕事への意欲も湧いてきます。
また、冬は年末年始やお祝い事も集中しやすいので、企業もそれに合わせて夏よりは高めに設定する場合も多いようです。
冬のボーナスをもらい2年目で退職してしまう社員もいる
労働者は法律によって守れているため、自分の意思で辞めたいと願い出れば、会社側はそれを拒否することはできません。冬のボーナスをもらってから退職することも可能ですし、無理に引き止めたり退職を認めないと言っても、一方的に退職できることができます。
退職届を出してから退職するまでに最低限2週間は必要ですが、その2週間を過ぎれば止める権利はなくなります。反対に、会社側から解雇するときは、労働基準法による厳しい規定が重視されますのでご注意ください。
- カネの悩み